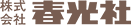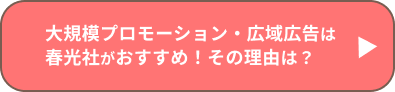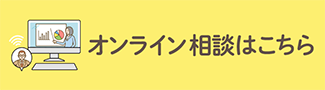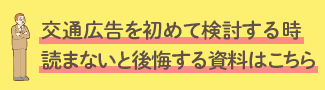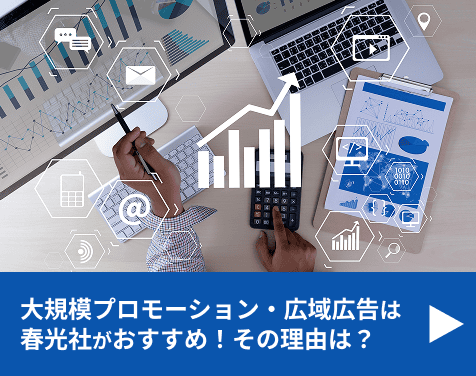お中元や季節の贈り物、新商品の発売——食品業界にとって、商品を「手に取ってもらう」きっかけづくりは重要です。そんなときに注目したいのが交通広告。駅や電車など、日常に溶け込む広告で、食品ならではの魅力をどう伝えるかがカギになります。本記事では、交通広告が食品業界に向いている理由や、食品商材に適した媒体など、実践的に解説します。
なぜ食品業界に交通広告が効果的なのか?
食品の広告は、消費者の「食べたい」という本能的な欲求をいかに刺激するかが問われます。交通広告は、そのための理想的な環境と特性を備えています
通勤・通学時に“おいしさ”を刷り込める接触環境
交通広告が持つ強みの一つは、反復訴求による「刷り込み効果」です。特に、多くの人が毎日同じ経路を利用する通勤・通学シーンでは、この効果が最大限に発揮されます。
繰り返し目にすることは、単なる認知獲得以上の意味を持ちます。人は、何度も接触する対象に対して、無意識のうちに親近感や好意を抱くようになります。これは「単純接触効果」として知られる心理効果です。食品広告においても、この効果は大きな力を持ちます。
その仕組みを簡単に解説します。
- 通勤・通学中の消費者は、リラックスしていたり、あるいは習慣的な行動の中で思考が自動化されていたりするため、広告に対する心理的な壁が低くなっています。
- この状態で、おいしそうな食品の広告が毎日繰り返し視界に入ることで、その商品やブランドが潜在意識に深く刻み込まれていきます。
- そして、仕事帰りや休日にスーパーやコンビニに立ち寄った際、棚に並ぶ多くの商品の中から、無意識のうちに見慣れた「あの広告の商品」に手を伸ばしやすくなるのです。
テレビCMのように番組を中断したり、ウェブ広告のようにコンテンツを遮ったりすることがないため、交通広告は生活者に嫌われにくいという特性も持っています。野村総合研究所の調査では、交通広告は「好きな広告」でトップに位置し、ネガティブなイメージが最も低い媒体であると報告されています。(※)この「嫌われにくさ」が、刷り込み効果をさらに高め、消費者の心に自然とブランドを浸透させる土壌となっているのです。
※参考:ジェイアール東日本企画と野村総合研究所が共同で 交通広告の価値研究を実施[PDF]
信頼性・品質感を担保する「公共性」のある広告
食品を選ぶ際、消費者が重視することの一つが「安全性」と「品質」です。特に新商品や馴染みのないブランドに対しては、誰もが慎重になります。ここで、交通広告の持つ「公共性」が、強力な信頼性の担保として機能します。
駅や電車、バスといった公共交通機関に掲出される広告は、各鉄道会社やバス会社が定める独自の厳しい審査基準をクリアしなければなりません。公序良俗に反するものや、消費者の誤解を招くような表現は当然ながら認められません。この審査プロセスが存在すること自体が、広告主とその商品に対する一種の「お墨付き」として機能します。
消費者は無意識のうちに、「公共の場に広告を出せるということは、信頼できるしっかりとした企業なのだろう」「多くの人が利用する駅で広告を見るのだから、人気のある商品なのだろう」と感じます。
デジタル広告が溢れる現代において、物理的な空間に存在し、社会的な信用を背景に持つ交通広告は、食品ブランドが最も大切にすべき「信頼」という資産を築き上げるための、確かな投資となるのです。
食品カテゴリ別メディア戦略
交通広告と一口に言っても、その種類は多岐にわたります 。商品の特性やターゲット顧客の行動パターンを深く理解し、適した媒体を戦略的に選択することが重要です 。ここでは、具体的な商品カテゴリとターゲットを想定し、どのような戦略が考えられるかを解説します。
ケース1:贈答用・高級品(高級菓子、季節のギフトなど)
贈答品は品質やブランドイメージに加え、「特別感」が重視される商品です 。購入者は大切な人への想いを託すため、じっくりと商品を選びます 。
- ターゲット・購買シーン: 品質やブランドイメージを重視し、特別な贈り物を探している人 。百貨店などでの購入を検討している段階。
- 場所: 百貨店や高級ブティックが立ち並ぶエリアの主要ターミナル駅 。
- 推奨メディア:
- 大型ポスター、デジタルサイネージ: 駅や電車といった公共交通機関の広告は、各鉄道会社が定める独自の厳しい審査基準をクリアしているため、その「公共性」が広告主と商品に対する一種の「お墨付き」として機能します 。消費者は無意識のうちに、「公共の場に広告を出せるということは、信頼できるしっかりとした企業なのだろう」と感じるため、特に安全性が問われる食品において、この信頼性の担保は強力な後押しとなります 。
▼推奨メディアの詳細は、以下よりご覧ください。
・駅デジタルサイネージ
・駅広告全般
ケース2:冷凍食品・チルド惣菜(冷凍パスタ、レトルトカレーなど)
「今日の夕食、どうしよう?」という日々の悩みに応える、実用性が重視される商材です 。ターゲットは忙しい会社員や主婦で、帰宅途中の献立を考えている瞬間を捉えることが重要です。
- ターゲット・購買シーン: 仕事や買い物の帰宅途中、夕食の献立を考えている会社員や主婦 。
- 場所: 通勤・通学で利用する路線や、スーパーマーケットに近い駅 。
- 推奨メディア:
- 電車内広告、駅広告: 「簡単、おいしい」といった実用性を、調理後の食卓イメージと共に具体的に見せることで、即時的な購買行動を促します 。帰宅途中の消費者に繰り返し情報を届けることで、反復訴求による刷り込み効果も期待できます 。
▼推奨メディアの詳細は、以下よりご覧ください。
・電車内広告全般
・駅広告全般
ケース3:常温品・日配品(調味料、ふりかけ、パンなど)
日常的に食卓にのぼる商品は、消費者の生活に深く浸透しています 。広告では、ブランドの再認知や新しいレシピの提案によって消費を喚起することが目的となります 。
- ターゲット・購買シーン: 日々の献立を考える中で、新しい食べ方やレシピのヒントを求めている生活者 。
- 場所: 生活動線上にある駅や電車内 。
- 推奨メディア:
- 電車内の中づり広告、駅ポスター: 電車内のように一定時間滞在する空間は、より詳細な情報を読ませるのに適しています 。季節の食材と組み合わせたレシピを紹介したり、QRコードでレシピサイトに誘導したりすることで、「いつもの商品」に新たな価値を発見させることができます 。
▼推奨メディアの詳細は、以下よりご覧ください。
・電車内中づり広告
・駅広告全般
ケース4:地域密着型商品(地元の特産品、飲食店など)
特定の地域に根差した食品ビジネスにとって、交通広告は地域住民との間に深い結びつきを築く強力な味方となります 。
- ターゲット・購買シーン: 地域住民の通勤・通学、買い物といった日常生活 。
- 場所: 地域の生活道路や、地元の駅 。
- 推奨メディア:
- バス広告、地方鉄道の広告: 地域の隅々まで運行するバスや鉄道は、住民の生活シーンで繰り返し接触するため、地域コミュニティの一員としての存在感を確立するのに効果的です 。これは、一過性のキャンペーンでは築けない、長期的な顧客との信頼関係を育みます 。
▼推奨メディアの詳細は、以下よりご覧ください。
・電車内広告全般
・バス広告
このように、効果的なメディア戦略は、消費者がどのような心理状態で広告に接触するかを考慮して設計されます。ギフトを選ぶ際の高揚した気持ちと、夕食の準備を考える実用的な思考では、響くメッセージも最適な場所も異なります。商品の特性と消費者の心理状態を掛け合わせることで、広告効果を高められるのです。
交通広告の相談はコチラ