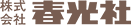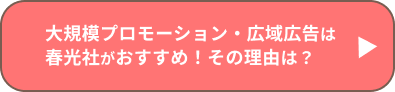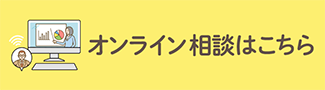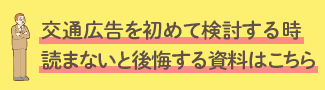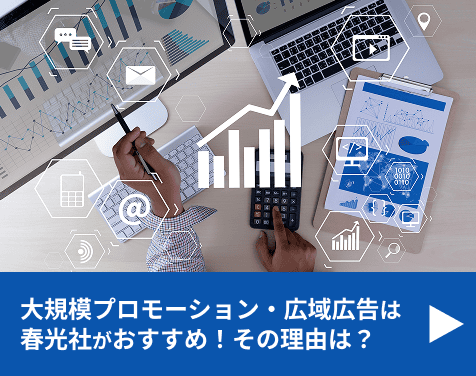求人広告を出しても応募が集まらないといった悩みを抱える企業の人事担当者にとって、大きな課題はまず知ってもらうこと。そんな時、生活導線上にある交通広告を活用することは、自社の存在を印象づける有効な手段です。この記事では、交通広告の本質的な効果に迫り、自社に合った人材を安定的に確保できる採用活動の土台づくりをサポートします。
交通広告が採用効果に期待できる理由
駅広告が採用に効果的な理由は、偶然ではありません。それは人間の心理原則に基づいています。このメカニズムを理解することは、広告投資の確信度を高め、戦略の精度を向上させます。
「毎日目にする安心感」が信頼をつくる
交通広告が採用に効く理由の一つは、「信頼される企業」というイメージをつくれる点にあります。これは、心理学で言う「ザイオンス効果(単純接触効果)」と、公共空間に掲出される広告が持つ社会的な安心感の両方が関係しています。
毎日通勤・通学で同じ駅を使う人にとって、何度も目にする企業広告は、「見覚えのある会社」へと変化します。この繰り返し接触は、親近感と共に「信頼できそう」という印象を自然と与えていきます。
さらに、その広告が駅や電車といった公共性の高い場所にあることも重要です。鉄道会社による掲出審査を通過した広告は、それだけで「きちんとした会社」と見なされる傾向があります。
知名度が浸透していない企業にとって、見たことがある安心感と信頼感の獲得は、採用活動の大きな後押しになります。
広告への自然な視線が注目を集める
ポップアップ広告や動画広告のようにコンテンツの視聴を妨げるWeb広告とは異なり、交通広告は環境の一部として存在します。そのため、見るか見ないかは利用者の自主性に委ねられており、広告への不快感が最小限に抑えられます。この「自主視認」という特性は、広告メッセージに対する受容性を高めます。
また、電車内やバスの車内は、一定時間滞在を余儀なくされる「閉鎖空間」でもあります。スマートフォンの画面から顔を上げたとき、乗客の視線は自然と車内広告へと向かいます。この「受動的でありながらも、自発的に見られる」というユニークな環境が、交通広告を極めて効果的なコミュニケーションチャネルにしているのです。
採用目的で選ぶべき駅広告の種類と使い分け方
駅広告:
- 駅ポスター広告 :交通広告の基本であり、比較的低コストで始められます。採用したい人材が多い大学の最寄り駅や、競合他社が集中するビジネス街の駅など、ターゲットを絞って掲出することで費用対効果を高めることができます 。
- 駅デジタルサイネージ:動画や動きのあるクリエイティブで注目を集め、特に若年層への訴求力が高いメディアです。静的な広告では伝えきれない「会社の雰囲気」や「働く人の表情」といった情報を伝えるのに適しています。
- 特殊広告(柱巻き・フロア広告など):駅空間全体をジャックするような強烈なインパクトで、記憶に残るブランド体験を創出します。そのユニークな見た目はSNSでの拡散も期待でき(二次的なメディア露出)、短期集中的な採用キャンペーンで大きな効果を発揮するでしょう。
電車内広告
- 中づり広告:車内で視認性が高いメディアの一つです。満員電車の中でも乗客の視線を集めやすく、採用イベントの告知や応募締切の案内など、タイムリーで「読ませる」情報発信に最適です。
- まど上・ドア横ポスター:ブランド構築の「主力」と言えるメディアです。1ヶ月以上の長期掲出が多く、着席・立席いずれの乗客の視界にも自然に入るため、ザイオンス効果を最大限に引き出し、企業の認知度をじっくりと浸透させます。
- 車内ビジョン:企業文化や働きがいといったストーリーを伝えられるツールの一つです。動画の力で、社員インタビューや「オフィスの一日」といった具体的なシーンを見せることで、候補者の共感を深く呼び起こします。ニュースや天気予報といったコンテンツと共に放映されるため、習慣的に視聴されやすいのも大きな利点です。
- 車両ジャック:電車1編成をまるごとジャックするブランディング手法です。圧倒的な没入感で強烈なブランド体験を生み出し、SNSでの話題化も期待できます。大規模な採用キャンペーンや、企業の新たな門出をアピールする際に大きな効果を発揮します。
バス広告
- 車体ラッピング・側面広告:「動く看板」として、特定の市区町村や沿線地域を繰り返し走行し、地域住民への高頻度なリーチを実現します。
- 車内広告(ポスター・ステッカー):特定の路線を利用する地域住民に深く、繰り返し訴求します。毎日利用する乗客にとっては日常の一部となり、地域に根ざした企業としての親近感を醸成します。
タクシー広告:
タクシーの車内タブレット(デジタルサイネージ)広告は、BtoB領域の専門職や経営幹部クラスの採用に適したツールです。タクシー利用者に多い経営層や富裕層といった、普段は広告が届きにくいターゲットに対し、プライベートな空間で、深く情報を届けることができます。BtoBのSaaS企業が営業目的だけでなく、同業界の優秀な人材を獲得するためにタクシー広告を活用するケースも増えています。
採用ターゲットに届く掲出場所の選び方
交通広告を出すと決めても、「どこに出せばいいの?」と悩むのは当然です。やみくもに広告を出しても、届けたい人に届かなければ意味がありません。ここでは、採用したいターゲット別に、どんな場所でどんな広告を出すのが効果的なのか、具体的な考え方を紹介します。
新卒・若手社員を採用したい場合
新卒や若手の採用で重要なのは、彼らの生活圏に入り込むことです。大学のキャンパス周辺や、彼らが日常的に利用する交通機関が狙い目になります。
特定の大学の学生にアプローチしたいなら、その大学の最寄り駅にポスターやデジタルサイネージを出すのが効果的です。
複数の大学の学生に広くアプローチしたいなら、学生の利用者が多い路線(例えば、都内なら中央線など)の電車内広告が有効です。また、大学キャンパスと駅を結ぶ路線バスに広告を出すのも、ターゲットに毎日接触できる良い方法です。
工場や店舗など、勤務地が限定されるスタッフを採用したい場合
勤務地がはっきりしている場合は、その地域に住んでいる人、あるいはその地域で働きたいと考えている人に直接アプローチするのが効率的です。
特にバス広告は地域密着の採用に強みがあります。工場の周辺や店舗の前を通る路線バスの車体にラッピング広告を出したり、車内ポスターを掲出したりすることで、地域住民に「近所で新しい募集があるんだ」と認知してもらえるでしょう。
また、その地域に住む人だけでなく、電車で通勤してくる可能性のある人にもアプローチできます。
経営幹部や管理職など、ハイクラス人材を狙う場合
経営層や管理職クラスの人材は、一般的な求人広告ではなかなか出会えません。彼らが利用する交通機関や場所に的を絞って、質の高い情報を届ける必要があります。
ハイクラス人材の採用において、タクシー広告は強力なツールです。経営層や企業の決裁権を持つ人々はタクシーの利用率が高く、一人きりの空間で広告が目に入りやすいという特徴があります。企業の将来性やビジョンといった、スケールの大きなメッセージを伝えるのに適しています。